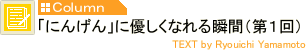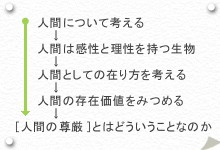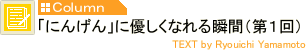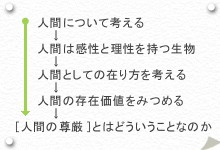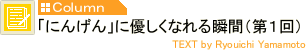
私なり考える社会福祉とは、
「人々が平等に暮らせること 心が常に穏やかであるということ」
そしてその対象となるに人々、即ち人間とは一体どういった存在なのかを考えていくことが、私が目指している福祉の原点となります。
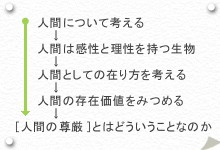
上述のことを基本視点として、今回から論進めていこうと思います。
[1.障害持った人たちへの思い]
何等かの「障害」を持っているということだけで、それが人間としての判断基準(人間的価値基準)のすべてを支配しているのではないでしょうか。
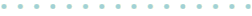 ほとんどの人が短絡的に社会的価値(人の役に立っているか、人に迷惑をかけてはいないか等)だけを追求し、それだけで、その人の人間的な価値判断の材料としてしまうことが間々あるようです。そればかりか、それを人間的価値基準と取り違えてしまう傾向にあります。ここに落とし穴があるのではと思います。それらの社会的価値が最高のものとされ、そういった意識構造が、本来の人間的価値を見誤らす結果を生んでしまっているように感じています。
ほとんどの人が短絡的に社会的価値(人の役に立っているか、人に迷惑をかけてはいないか等)だけを追求し、それだけで、その人の人間的な価値判断の材料としてしまうことが間々あるようです。そればかりか、それを人間的価値基準と取り違えてしまう傾向にあります。ここに落とし穴があるのではと思います。それらの社会的価値が最高のものとされ、そういった意識構造が、本来の人間的価値を見誤らす結果を生んでしまっているように感じています。
ここで気をつけなければならないことは、社会的にはどうであれ、障害者が求める「真の価値なるもの」即ち、障害を持った人たちに必要とされる「本質的価値」とは何かをどう想定することだと思うのです。何か他人より抜きん出たことができたり、たくさんのものが作れたり、うまくしゃべれたりすることが、その人の人間的存在価値の総てではないということを理解しなければならないということなのです。
必要なことは、私たちが、障害を持った人たちに「人間としての人格と存在」を認められた自分を感じてもらえるかどうかということでもあるわけです。
視点を変えれば、今の社会的価値偏重の社会が、障害者の人間的価値までも押し潰してしまっている現実があるということなのです。圧倒的多数の障害を持たない人たちが、少数の障害を持った人たちの存在を、価値ある人として認めていないということでもあるわけです。
ここに、人としてのメンタルな意識改革が、私たち「人間」には大いに必要だということの必然性があります。
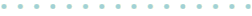 「障害」とは、人間の表面に現れたほんの一部に過ぎないということは、様々な場面で聞くことができます。そしてそれは、言うならば単に一つの「性格」に過ぎないともいわれているのは、ノーマライゼーションの一端でもありと考えます。よって、それはその本質であり総体であるはずの「人間」の価値基準には到底なりえないということなのです。
「障害」とは、人間の表面に現れたほんの一部に過ぎないということは、様々な場面で聞くことができます。そしてそれは、言うならば単に一つの「性格」に過ぎないともいわれているのは、ノーマライゼーションの一端でもありと考えます。よって、それはその本質であり総体であるはずの「人間」の価値基準には到底なりえないということなのです。
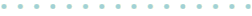 もし人間としての評価が必要ならば、それは「人格」でなされなければならないと思います。
もし人間としての評価が必要ならば、それは「人格」でなされなければならないと思います。
本来、人を人が評価することはあまりいいことではないと思うのですが、もしそれが必要で、それをしなければならない時、私たちが気をつけなければならないことは、また人を評価するときの私たちのあやまちは、その人格ではなくその「能力」だけで判断してしまうということです。能力的に低位な人は人格的にも低位に見られてしまう、ということがあるのです。
結局、その人の表面に現れたものだけで、その人を全部見切ったかのような判断をしてしまっています。しかし、それがその判断が、その人をすべて支配してしまうことになってしまえば、それは人そのものの存在価値までも否定してしまうことにもなってしまう危険性があるということもいえます。
「障害とは」一体どういうことなのか、一体どういったものなのか、もう一度捉えなおす必要があると思います。
みんな同じ「人間」なんだから
Yamamoto福祉介護研究会
代表 山本亮一
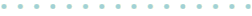 この福祉のコーナーへのご意見、ご感想、山本亮一さんへのお便りも、編集部あていただければ幸いです。
この福祉のコーナーへのご意見、ご感想、山本亮一さんへのお便りも、編集部あていただければ幸いです。



|